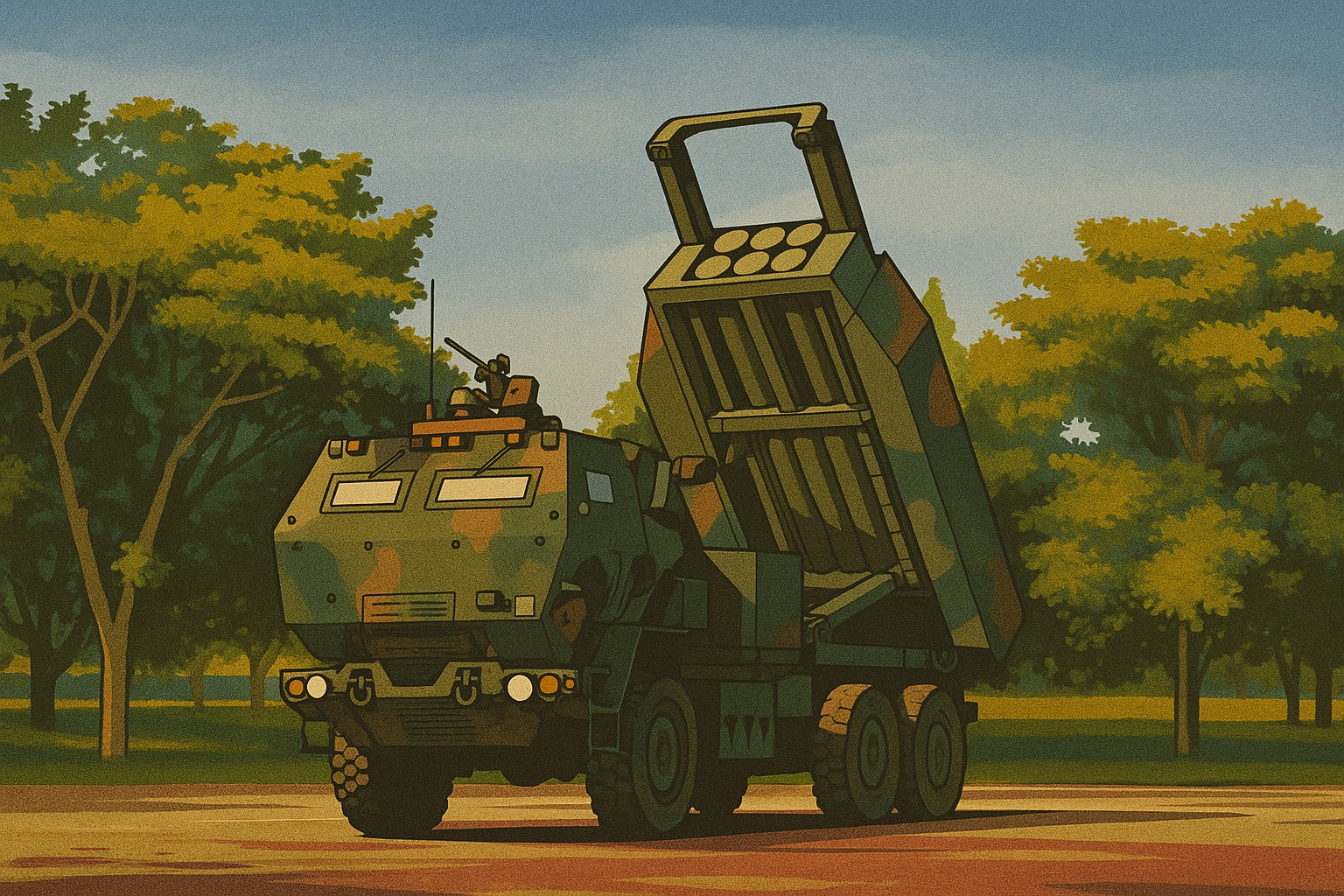F16納入遅延が象徴する防衛調達の危機
台湾の対米武器調達が相次ぎ遅延し、頼清徳政権の掲げる「台湾の盾」構想が揺らいでいる。国防部によると、米国からの主要調達25案件のうち、F16C/Dブロック70戦闘機、AGM154精密誘導弾、Mk48魚雷、M1A2戦車、MQ9無人機、スティンガー携行ミサイルなどの納期がいずれも延びている。戦力整備や訓練スケジュールにも影響し、台湾海峡有事の際には「第一撃」に耐える能力が損なわれるおそれがある。
特に深刻なのが、総額約2400億台湾元に及ぶF16C/Dブロック70の調達計画だ。台湾は66機を発注し、2025年3月に米国で1号機の出荷式が行われたが、システム統合上の不具合で試験飛行が始まらず、納入は一機も完了していない。顧立雄国防部長は立法院で「来年末までに全機納入は難しいが、一部は引き渡される」と述べた。台湾はすでに総額の約6割に当たる48億ドルを支払い済みだが、ロッキード・マーチン社の生産能力は年23〜26機にとどまり、完納には数年を要する見通しだ。
[出典]聯合報
国産装備にも遅れ 海鯤級と雲豹の課題
遅れは米国製装備だけではない。台湾が自主建造する海鯤級潜水艦も、戦闘システムや魚雷発射装置など米国製部品の輸出承認が遅れ、建造工程に影響している。また、雲豹(CM-32)装甲車は台湾車輛公司が開発した国産車両だが、米カミンズ社製エンジンなど一部部品の供給が不安定化している。
これらの遅延は、台湾が「防衛自主化」を掲げながらも、依然として米国や欧州の部品供給に依存する構造を示している。国防部は「2027年が台湾にとって最も危険な時期」と警鐘を鳴らしており、装備の遅れは地政学的リスクを高めている。
[出典]中国時報
米依存構造からの脱却へ 「防衛主権」確立の必要性
専門家は、頼政権が掲げる「非対称戦」や「防衛持続力」を現実化するには、四つの方向が必要だと指摘する。
① 外国依存を減らし、防衛産業の主体性を確立すること。
② 米政府に技術的支援を求め、メーカー側の問題解決を促すこと。
③ 地域安全保障戦略の枠組みを明示し、米台協力を戦略レベルで位置づけること。
④ 野党による監督を対外交渉の交渉力に転化すること。
国防自主化は一朝一夕には進まないが、欧州からの技術移転や国内防衛基金の拡充が「任督二脈」となる。日本のF3、韓国のKF21のように、技術連携による共同開発が重要なモデルケースとされる。
「台湾の盾」を現実の防衛力に変えるために
防衛費をGDP比5%に引き上げる方針を示した頼政権だが、装備の納入遅延と国産開発の停滞が続けば、構想は理想に終わりかねない。軍購遅延は単なる物流上の問題ではなく、米国の軍産複合体の構造的限界と、台湾が抱える依存体質の双方を映し出している。
頼政権が「台湾の盾」を現実の防衛力に変えるためには、装備の調達と国産化を同時に進める二正面戦略が不可欠である。