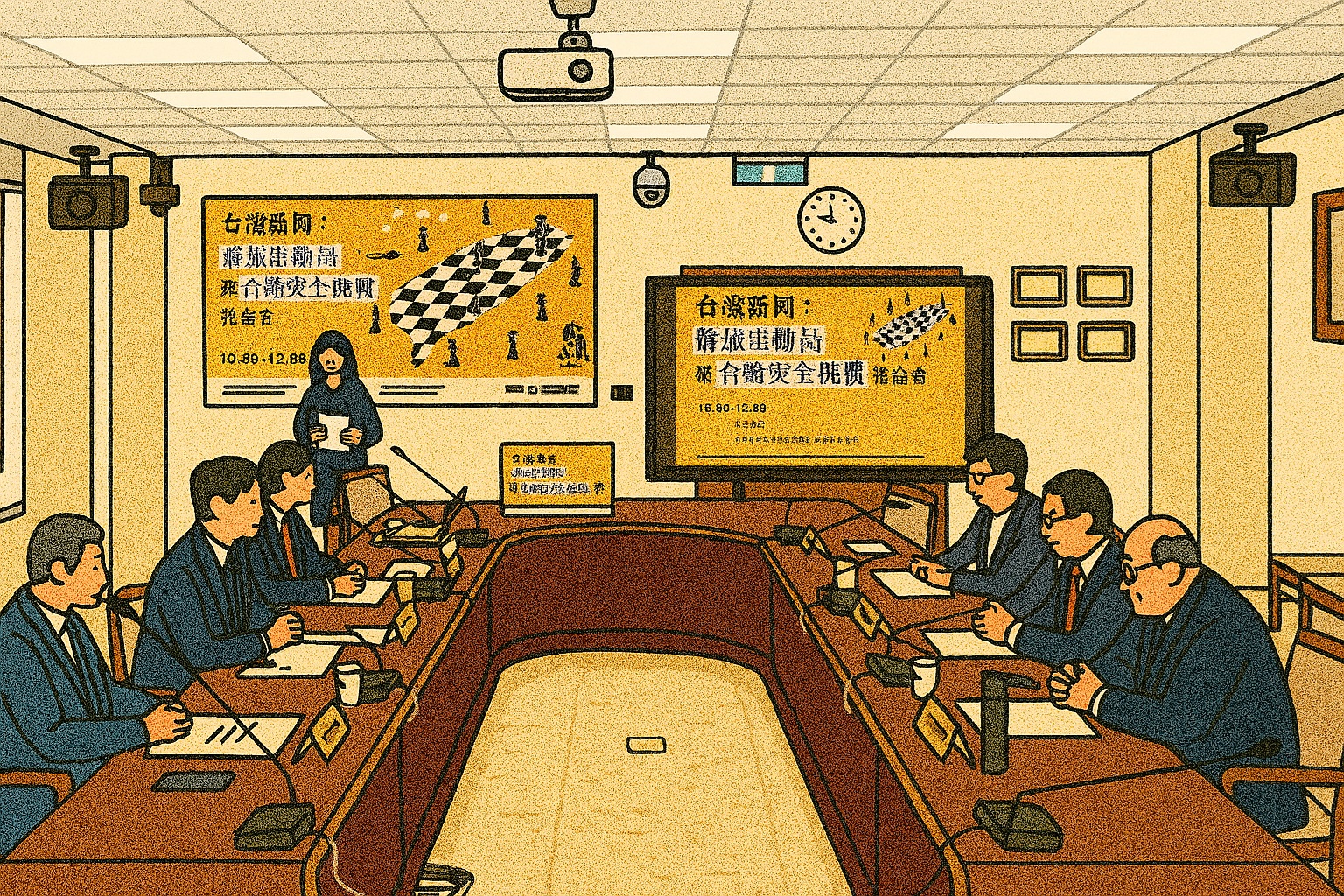中国軍の戦略が転換、「灰色地帯」から「実戦配備」へ
中国人民解放軍の台湾周辺での活動が変質している。台湾・政治大学国際関係研究センターが開いた座談会「台湾海峡の新局面:人民解放軍の動向と台湾の安全保障上の挑戦」では、複数の専門家が「共産軍の行動はすでに『灰色地帯』から『実戦配備』段階に移行した」との認識を示した。
国防大学の馬振坤教授は、軍機や艦艇による威嚇行動が減少する一方、爆撃機の活動が急増していると説明。9月には轟6(H-6)シリーズ爆撃機が台湾海峡正面で14日間活動し、平均2日に1回の頻度だったという。これらの機体は中距離打撃任務を担い、これまで台湾南西空域やバシー海峡で行動していたが、最近は台海正面に進出し、無人機を伴って体系的な打撃力を形成。「作戦能力が成熟すれば、外科的な精密攻撃が可能になる」と警告した。
馬氏はまた、「中共中央軍事委員会副主席の何衛東が今年4月から公の場に姿を見せなくなって以降、中国軍の活動が大きく変化した」と指摘。灰色地帯行動の副作用が明らかになるなか、もう一人の副主席・張又侠が主導する「実戦路線」への転換が進んでいるとみられる。「見かけ上は威嚇が減っても、実際の脅威は増している」と述べた。
「2027年ではなく2035年」が焦点=軍改革と教育成果が成熟
国防安全研究院の亓楽義助理研究員は、中国軍が掲げる「2027年建軍百年目標」は“武力統一”を意味しないと強調。「真の高リスク期は2035年」とし、「この年に軍制改革の成果が成熟期を迎え、非対称・非接触・非線形の『三非作戦』を展開できる」と指摘した。
2035年は、習近平国家主席が提唱した「国防・軍隊現代化三段階戦略」の第2段階にあたる。中国軍はこの時期に連合作戦能力を完成させ、最小コストで短期決戦を遂行できる水準に到達するとの見方が強い。
淡江大学の林穎佑副教授も「2035年は人材面から見ても転換点」と指摘。2017年に軍校が統合されてから18年を経る2035年には、当時の士官が中佐・大佐級に成長し、部隊の中核を担うようになる。「新教育制度の成果が現れ、若手将校世代が指揮層に台頭する」と分析した。
米国防総省「台湾軍は全面改革が必要」 防衛費10%案も支持
同日、米上院軍事委員会で国防総省インド太平洋安全保障担当次官補候補のジョン・ルー氏が証言し、「台湾は複数の分野で抜本的改革を行う必要がある」と強調した。訓練、動員、軍民統合、基礎施設防護、サイバー防衛などの体制強化を挙げ、「武器供与だけでなく即時的かつ構造的な改革が必要だ」と述べた。
さらにルー氏は「台湾軍の防衛費をGDP比10%に引き上げることを支持する」と表明し、台湾が差し迫った生存の脅威に直面していると警告した。
台湾の防衛環境、危機の深化
座談会を主催した政治大学国際関係研究センターの王信賢主任は、「今後、兵棋推演と戦略シミュレーション学院を設立し、学生や研究者に台湾の現実的安全保障環境を理解させる」と述べた。
馬振坤氏は「中国軍が当面、軍事手段による解決を選ぶ可能性は低いが、必要と判断すれば即応体制にある」と強調。灰色地帯行動が減少する裏で、実戦能力が向上している現状を踏まえると、台湾の防衛改革と国際連携は待ったなしの課題だと訴えた。
(出典:中央社、聯合報、CDNS 2025年10月8日)
出典
- 中央社:共軍犯台高風險期 學者推估2035年 — https://www.cna.com.tw/news/acn/202510080262.aspx
- 聯合報:共軍機艦台海周邊活動變少 軍事專家:「灰區」轉為「實戰」取向 — https://udn.com/news/story/7331/9057322?from=udn-ch1_breaknews-1-0-news&utm_source=chatgpt.com